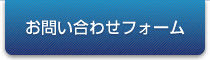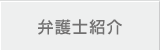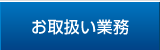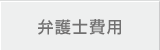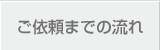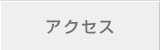お取扱い業務
下記のコンテンツは順次公開中です。現在は青文字のコンテンツのみ公開中です。その他につきましては、暫くお待ちください。
法人事業再生
法人事業再生の流れ
民事再生スキームを用いた法人事業再生の標準的な流れをご説明いたします。案件によってはこれとは異なる流れとなりますので、詳細は当事務所までご相談ください。
- 1 当事務所でのご相談
- 各種資料をお持ちいただき、経営状態や事業の将来性を確認の上、事業再生に適するか否かを検討します。申立費用や、申立後当面の運転資金が必要なので、資金が枯渇する前にできるだけ早くご相談ください。
再建可能性が薄い場合には、この時点で事業再生を断念し、破産手続等を検討することになります。 - 2 申立前準備
- 申立前には、申立書の作成のほかにも、民事再生関連の基幹的な業務を担当する少数精鋭の従業員の選抜、債権者説明会の会場や資料等の準備、当座の運転資金の確保など、やるべきことがたくさんあります。
民事再生申立のXデーは、資金の出入りや口座凍結・相殺の危険性などとの兼ね合いを見極め、慎重に決定します。 - 3 民事再生申立・保全処分及び監督命令の発令
- 裁判所に対して、債務額に応じて決定される予納金を納付した上で、民事再生申立を行います。
民事再生申立と同時に、裁判所から弁済禁止等の保全処分が発令されます。この日以後は、債権者に対する一切の弁済(一定の少額債権や賃貸物件の賃料などは除かれることが多いです)を止め、会社再建のための体制構築に入ります。民事再生申立を知った債権者から取り付け騒ぎや物品の引揚げ要求等がなされることがありますが、毅然とした対応をとります。
また、裁判所は、民事再生手続が適法適正に行われているかを監督するために、監督命令を発令し、監督委員を選任します。この監督委員による監視と協力の下、民事再生手続を進めていくことになります。 - 4 債権者説明会開催
- 申立後まもなく、会社が主催する第1回債権者説明会を開催し、債権者に対して民事再生申立に至ったことをお詫びし、その経緯や今後の流れを説明します。
- 5 民事再生手続開始決定
- 東京地裁の標準的なスケジュールの場合、申立から1週間程度で、民事再生手続開始決定が出されます。
- 6 財産評定・債権調査
- 会社に財産がどのくらいあるのかを評価し、これを裁判所に報告するのが、財産評定です。現時点で破産した場合の配当と、民事再生によって経営再建した場合の配当とを比較する基礎的な資料となります。
また、会社に債務がどのくらいあるのかを調べるのが債権調査です。会社が把握している債権者に対して民事再生手続開始決定通知と債権届出用紙を送り、債権者からの債権の届出を待ち、届出のあった債権について会社がこれを認めるか認めないか(認否)の意思表示をするといった手順で調査されます。 - 7 再生計画案の作成・提出・可決・認可
- 債務カットの割合を示し、これをいついかなる方法により弁済していくのかを示すのが再生計画案です。この再生計画案について債権者に賛成(債権額をベースとした議決権額の過半数と、債権者の頭数の過半数という2要件をクリアする必要があります)してもらえなければ民事再生は失敗に終わり、必要に応じて破産手続に移行することになります。破産した場合に比べて債権者に有利であることと、計画が現実的であることとの両方をアピールできるような計画を立案し、監督委員やメインバンクなどの主要債権者と協議しつつ修正を加えていき、可決の見込がたった段階で裁判所に提出します。
債権者集会において再生計画案を採決し可決した後、裁判所が認可決定を出し、これが確定することで、再生計画案に従った会社再建が始まります
東京地裁の標準的なスケジュールの場合、申立から3ヶ月程度で再生計画案の提出期限を迎え、申立から5ヶ月程度で再生計画案が認可されます。 - 8 再生計画の履行
- スポンサーがついて一括で支払えるといった事情が無い限りは、分割弁済期間を法定最長期間である10カ年計画とすることが多いです。誠実に再生計画を履行し、会社の再建を図ります。
再生計画の履行に困難が生じた場合には、再生計画の変更や、破産手続への移行を検討することになります。